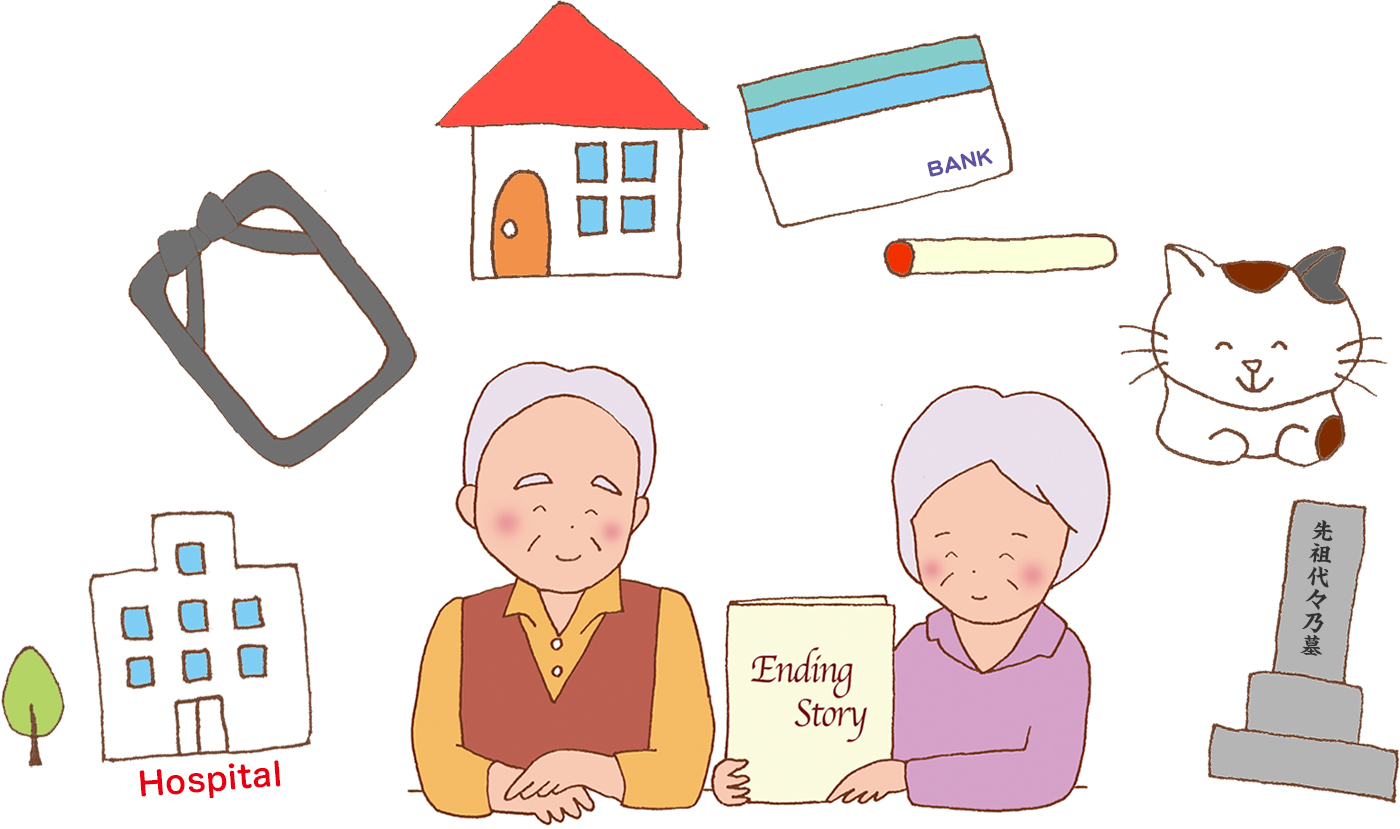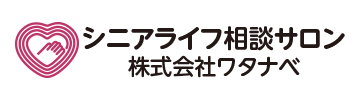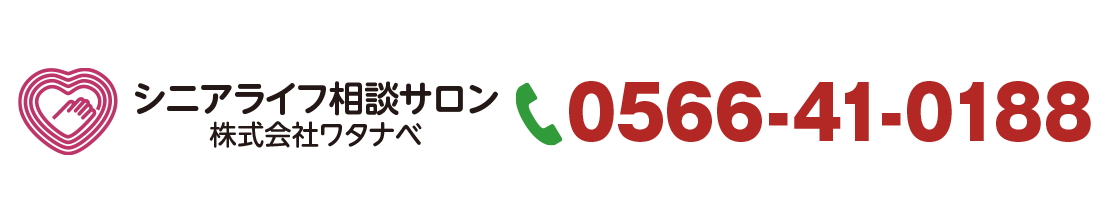元葬儀社社長が考える「遺言書」その効果
2.自筆証書遺言の作り方
自筆証書遺言とは、財産目録を除き遺言者が紙に自ら内容を手書きして、かつ、日付、氏名を書いて、署名・押印することにより作成する遺言のことです。
【ポイント】
1 全文を自筆すること。
民法改正により自筆証書遺言の方式が緩和され、財産目録はパソコン等で作成することが認められました。また、登記事項証明書や預金通帳の写しをそのまま利用することもできます。ただし、遺言者は、その目録のページ(両面記載した場合は、その両面)ごとに、署名し、押印しなければなりません。本文(財産目録以外)は、全て自筆することが必要です。
2 日付を書くこと。
「令和2年4月吉日」、「令和2年4月」という書き方はいけません。「令和2年4月 17 日」などと書きましょう。
3 名前を書くこと。
4 押印があること。
押印する印鑑に決まりはありませんが、実印を用いるのが望ましいと考えます。
5 15歳以上であること。
以上の一つでも要件が欠けた場合は無効です。
【要注意】自筆証書遺言書保管制度の利用、検認手続をしても、上記の要件を満たしていない場合は有効になりません。
*財産目録はパソコンで作成、代筆でもOk
検認手続き
自筆証書遺言は、検認手続きを経た遺言書でなければ、金融機関、法務局等では受理されません。
- 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
(民法第 1004 条)
- 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。(民法第 1005 条)
※封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち合いの上、開封しなければなりません。
検認の申し立ては、遺言者の出生時から死亡時までの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
また、検認の申し立てをしても、検認を行う期日は、後日、裁判所が決めるため、相続執行までに時間を要することがあります。
法務局における自筆証書遺言書保管制度により、法務局に預けた自筆証書遺言は検認手続が不要です。
元葬儀社社長が考える「遺言書」自筆証書遺言の作り方